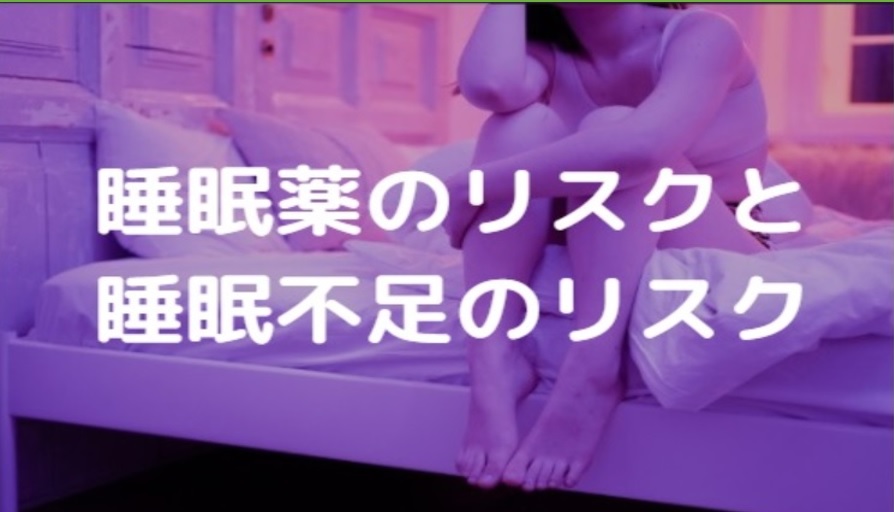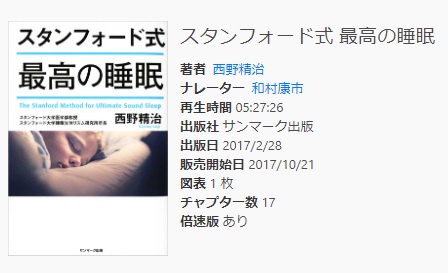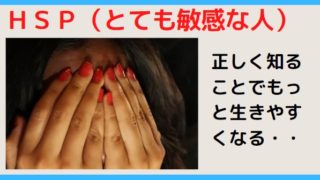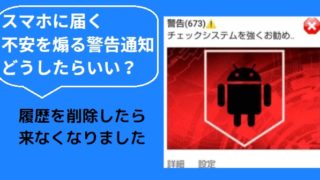眠れない夜は辛いものですね。
そんな時は、ついつい睡眠薬に頼りがちになってしまいます。
眠れないから睡眠薬を服用する
薬を飲むと眠れるけど、同時に睡眠薬のリスクも考えないといけません。
眠れない夜は一時的に不眠が解消されていいかもしれませんけど
長期に渡って、睡眠薬に頼ることに問題はないのでしょうか?
人はどうして眠るのでしょう?
脳を休める為とか、身体の組織の修復を行っているとかいろいろ言われますが、
単純に、眠くなるから寝るというのが、自然なことですね。
寝る時間になっても、眠くならないということは不自然なことです。
どこかで自然に逆らった生活をしていないでしょうか?
夜に強い光を浴びたり、朝遅くまで寝ていたりしていませんか?
薬に頼る前に、日頃の生活を見直してみてはいかがでしょう。
目次
睡眠薬のリスク
眠れないからといって、すぐに睡眠薬に頼るのは正解でしょうか?
最初は眠れない時だけに飲んでいても、
そのうち服用回数が増え、
毎晩服用するようになったら、もう薬なしでは眠れなくなります。
睡眠薬を使う前に、規則正しい生活をしてみたら、眠れるようになるかもしれません。
どうしても、睡眠薬を服用するなら
睡眠薬のリスクも知ったうえで、服用したほうがいいです。
<睡眠薬のリスク>
・依存性がある
・反跳性(はんちょうせい)不眠になる
・認知症のリスクが高まる
・転倒のリスクがある
依存性がある
長期間使用しているうちに効かなくなり、
そのために用量を増やしても、またある程度時間が経つと効かなくなる。
量を増やしたり、薬の種類を変えるうちに、薬の量が増えていく。
繰り返し薬を摂取することで、効果が切れてきたときに脳が自動的に薬を欲します。
急に薬を摂取しなくなると離脱症状と呼ばれる身体の症状が起こります。
不眠、不安、イライラ、焦燥、頭痛、吐き気、抑うつなどです。
反跳性不眠(はんちょうせいふみん)になる
睡眠薬を使って眠れるようになっても、
いざ薬を中断すると逆にひどい不眠症に悩まされること
睡眠薬を中断する際は漸減法といって、
用量を徐々に減らすなど注意深く減らす必要があります。
認知症になるリスクが高くなる
ベンゾジアゼピン系の睡眠薬を投与されている高齢者は、
投与されていない高齢者と比べて43~51%ほどもアルツハイマー型認知症になりやすく、ベンゾジアゼピン系の使用量が多く、使用歴が長いほど
アルツハイマー型認知症になるリスクが高くなることが分かっています。
ベンゾジアゼピン系の睡眠薬とは?
睡眠薬には、『ベンゾジアゼピン系』『非ベンゾジアゼピン系』がある。
現在使われている睡眠薬の中で、メインを占めているのが『ベンゾジアゼピン系』という系列の薬です。
脳の活動(興奮)を抑えることで眠りやすくし、睡眠障害などを改善する薬。
脳内で神経興奮に関わるベンゾジアゼピン受容体(BZD受容体)を
薬で刺激することで、脳の興奮が抑えられ眠気などがあらわれる。
| ベンゾジアゼピン系 | 非ベンゾジアゼピン系 | |
| メリット | ・即効性がある ・効果をある程度予測できる ・不安や筋肉の緊張が和らぐものもある |
・睡眠が深くなる ・翌朝の眠気やふらつきなどの副作用が少ない ・依存性が少ない |
| デメリット | ・睡眠の質が落ちる ・ふらつき、翌朝への持ち越し、健忘などの副作用 ・依存性がある |
・効果が中等度 ・種類が少なく超短時間型しかない ・健忘の副作用が多い |
| 主な薬名 | ・ハルシオン ・レンドルミン ・エバミール、ロラメット ・リスミー ・サイレース(中間型) ・ユーロジン(中間型) |
・マイスリー ・アモバン ・ルネスタ |
| 備考 | ベンゾジアゼピン系睡眠薬は、昔の睡眠薬に比べると安全性も高まり、抗不安や筋弛緩の効果も期待できる薬。 でも、浅い眠りを増やしたり、効きづらくなってしまうデメリットもある |
「寝つきが悪い」という人には有効だが、中途覚醒や早朝覚醒がある方には効果が認められないことがある |
<出典https://cocoromi-cl.jp/knowledge/psychiatry-medicine/sleeping-drug/benzodiazepine-point/>
私は、たまにデパスを処方してもらいますが、
デパス(抗不安薬、睡眠導入剤)はどちらにもあてはまらないけど、
ベンゾジアゼピン系と同様の作用を持つということです。
転倒のリスクがある
睡眠薬の副作用に
「脱力」「ボーッとする」「注意力・集中力の低下」などがあり、
転倒のリスクも高まります。
睡眠不足のリスク
睡眠が足りていないと、ボーッとして、頭がスッキリしませんよね。
やる気が起きず、仕事もあまりはかどりません。
眠っている間に私たちの脳と身体では何が行われているのかというと
自律神経や脳内化学物質、ホルモンが休みなく働いているそうです。
眠らないと身体にどんな影響がある?
■集中力が低下し、事故やケガを招きやすい
■インスリンの分泌が悪くなって血糖値が高くなり糖尿病をまねく
■新陳代謝の低下により、体重増加や肥満につながりやすい
■交感神経の緊張状態が続いて高血圧になる
■精神が不安定になり、うつ病・不安障害・アルコール依存・薬物依存の発症率が高くなる
■認知症にかかりやすくなる

不眠症と睡眠不足は違う
眠れないから睡眠不足になり、翌日のパフォーマンスに影響します。
でも、不眠症と睡眠不足は違います。
| 不眠症 | 眠ろうとしても「眠れない」状態
・寝つきが悪い |
|---|---|
| 睡眠不足 | 「床で休む時間が不十分で、日中に眠気を感じる状態」 |
睡眠は8時間とらないといけないという思い込み
私たちはなぜか、理想の睡眠時間は8時間という思い込みがないでしょうか?
人は人生の1/3を眠るという言葉があるからでしょうか。
理想の睡眠時間は?
年齢によっても睡眠時間は変化し
産まれたばかりの赤ちゃんは1日中うとうとしているけど、
老人になると、6時間程度の睡眠で充分足りるということです。
睡眠の研究で、
睡眠時間が短い人、あるいは極端に長い人では
高血圧、糖尿病の罹患率が高いことが明らかになっています。
さらに、米国における 110 万人対象の調査で、
睡眠時間は短くても長くても不健康で、
6 時間から 7 時間台が最も死亡率が低かったという結論が出ています。
8 時間睡眠は根拠がなかったといえます。
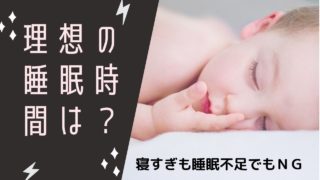
昔の人の眠りと今の眠りの違い
睡眠の歴史を調べた学者がいます。
バージニア工科大学の歴史学教授のエカーチ博士の研究によると、
照明がない時代や、照明がない地域の眠り
■「照明が普及する前、産業革命以前のヨーロッパでは、
日が暮れるとすぐに眠るのだが、
3時間程度でいったん起きて、
夜がふけてから再び3~4時間眠っていたという。このような二度寝によって、6~7時間眠るのが一般的だったようだ。
■「アフリカや南米奥地で電気を知らない部族の生活を調べた最近の報告
寝床で7~8時間を過ごすが、
そのうち眠るのは6~7時間であることが分かった」照明がなかったからといって、9時間も10時間も眠っていたわけではないということだ。
まとめ
私は、中途覚醒して眠れないとすぐに睡眠薬を飲んでいました。
毎日ではないのですが、週に2~3回ほどは服用していました。
でも、睡眠薬を飲んだ翌日は眠気が残り、ボーッとする感じが嫌で
なんとか薬を飲まずに眠れればと考えていました。
ある夜、すぐに薬を飲むのを止めて、
寝るのをあきらめて、本を読んだりしながら2時間くらい起きていて
また再度眠るというふうにしたところ、翌日そんなに睡眠不足を感じませんでした。
それから、無理に睡眠薬を飲まなくてもいいということが分かりました。
夜中に2時間くらい起きていても、
トータルで6時間くらい眠れると、そう日中に影響はないということが分かりました。
睡眠の研究からも、
夜中に目が覚めるのは、実は自然なことだと知り、なんだか安心しました。
睡眠薬に頼りすぎるのはよくないと分かっていながらも、
眠れない辛さの方が勝ってしまうと、
どうしても睡眠薬に手が伸びてしまいがちですけど、
睡眠薬の怖さもぜひ、知っていてほしいです。